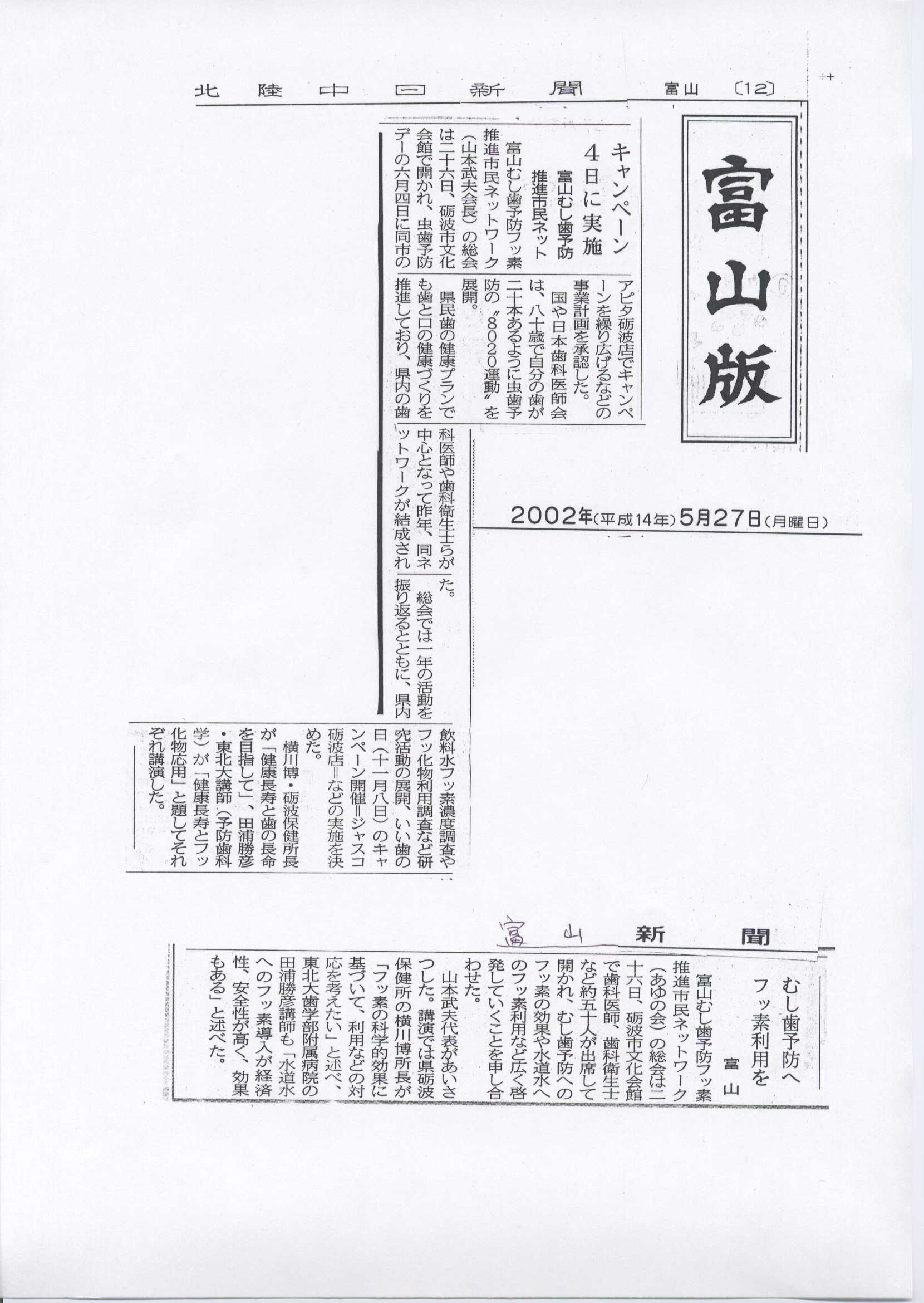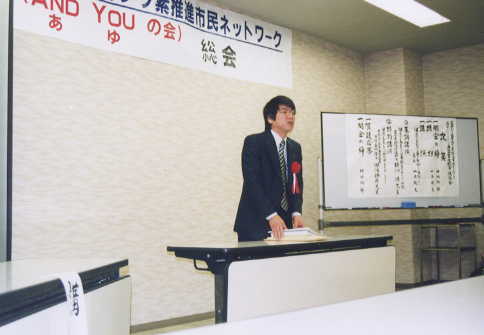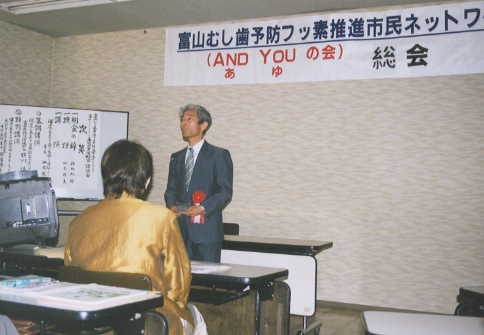| And You (あゆ) の会平成14年度総会・講演会報告 |
日時 平成14年(2002年)5月26日(日)午前10時〜午後1時
場所 砺波市文化会館 多目的ホール2階研修室
平成14年5月26日、富山むし歯予防フッ素推進市民ネットワークの平成14年度総会・講演会には、スタッフを含め70名を越える参加者がありました。遠くは福井県から、また、金沢市からも昨年に続いて参加されました。横川砺波保健所長さんの含蓄のある講演は、これからの地域保健の担い手として、われわれがどのような心構えをしていくかの指針となりました。また、東北大学歯学部の田浦勝彦先生の講演は、フッ素についてわかりやすく話され、如何にむし歯予防に大切なものであるか、「誰にでもできる 小さな努力で 確かな効果」のフロリデーション(水道水フッ素濃度適正化)がどれほど必要かを、訴えられました。今年の総会は、大変意義深いものになりました。
また、お忙しい中、取材をしていただいた、富山新聞、北陸中日新聞に感謝いたします。その内容を紹介いたします。(山本武夫)
−2−
富山新聞(平成14年5月27日記事) 『むし歯予防へ フッ素利用を』 富山
富山むし歯予防フッ素推進市民ネットワーク(あゆの会)の総会は26日、砺波市文化会館で歯科医師、歯科衛生士など約50人が出席して開かれ、むし歯予防へのフッ素の効果や水道水へのフッ素利用など広く啓発していくことを申し合わせた。
山本武夫代表があいさつした。講演では県砺波保健所長の横川博所長が「フッ素の科学的効果に基づいて、利用などの対応を考えたい」と述べ、東北大学歯学部附属病院の田浦勝彦講師も「水道水へのフッ素導入が経済性、安全性が高く、効果もある」と述べた。
北陸中日新聞(平成14年5月27日記事) 『キャンペーン 4日に実施』富山むし歯予防推進市民ネット
富山むし歯予防フッ素推進市民ネットワーク(山本武夫会長)の総会は26日、砺波市文化会館で開かれ、虫歯予防デーの6月4日に同市のアピタ砺波店でキャンペーンを繰り広げるなどの事業計画を承認した。
国や日本歯科医師会は、80歳で自分の歯が20本以上あるようにむし歯予防の”8020運動”を展開。
県民歯の健康プランでも歯と口の健康づくりを推進しており、県内の歯科医師や歯科衛生士が中心となって昨年、同ネットワークが結成された。
総会では1年の活動を振り返るとともに、県内飲料水フッ素濃度調査やフッ化物利用調査などの研究活動の展開、いい歯の日(11月8日)のキャンペーン開催=ジャスコ砺波店=などの実施を決めた。
横川博・砺波保健所長が「健康長寿と歯の長命を目指して」、田浦勝彦・東北大学講師(予防歯科)が「健康長寿とフッ化物応用」と題してそれぞれ講演した。
|
基調講演『健康長寿と公衆衛生の果たす役割』 富山県砺波保健所長 横川 博 先生
(講演要旨)
公衆衛生学の教科書によると、ウィンスローの定義では、『公衆衛生』とは、人々の健康のための社会環境のシステム・制度づくりまでを含め、近代では、上下水道の整備や社会保障制度の整備なども考える社会学的要素を含む。
『健康長寿』は、本来『公衆衛生』が主務の保健所が果たす言わば当然の役割である。しかし、従前の、伝染病の制圧などから、近年の生活習慣病の克服などへ、従来の手法が使えないものが出てきてはいるが、対応が遅れている。
そうして、ごく最近になって、新しいプラン作りが始まった。『健康日本21』が、それである。従来の行政手法はやりっぱなしという面が多かった。健康日本21では、特に『EBM(科学的根拠に基づく医療)』が重視され、公衆衛生に関する事業も評価され、さらにフィードバックされてより有効な方法を展開できるようにする。役所も成果を上げなければならない。実際にどのように評価されるか、現場には戸惑いもある。
歯科の問題では、「フッ化物洗口を行い、むし歯が減少した」ということを、科学的根拠に基づき、学問的探求をして、どのように評価を行うかその技術がこれから問われる。一般に分かりやすく解説してもらいたい。
そのように、これからは、システムとマンパワーが鍵を握る。従来型から切り替える必要がある。感染症対策も一部で結核のように再発してきたものもあり、生活習慣病対策と合わせて、それぞれにしっかりと認識して頂かないといけないが、重要なのは正しい情報を提供することである。マスメディアなどや、ITなども活用しなければならない。
それから、公衆衛生がすそ野を広げるには、ヘルスボランティアなどのボランティアグループの活躍を期待するものである。
歯科医や歯科衛生士も、従来の個別の指導から、幅広く社会医学の観点で広く、健康の状況の改善を求めるよう活躍してもらいたい。
公衆衛生の最前線は市町村の保健センターであるが、ヘルスボランティアなどのリーダーを束ねることを要求される。そことも協力して、歯科医は活躍してもらいたい。
横川 博先生 ご略歴
昭和32年生まれ、昭和57年3月に自治医科大学医学部を卒業される。昭和57年6月〜59年3月より、県立中央病院にて研修され、昭和59年4月〜63年3月、内科医として黒部市民病院、城端厚生病院、利賀村診療所に勤務される。昭和63年4月から、八尾保健所勤務、以後小杉保健所、魚津保健所、高岡保健所小杉支所に勤務され、平成12年11月より、県立砺波保健所長で、現在に至る。 |
−3−
特別講演「う蝕予防と適切なフッ化物応用ーフロリデーションー」
東北大学歯学部附属病院予防歯科 講師 田浦勝彦先生
|
(講演内容)
人はだれでも、心身共に健康で、生き甲斐をもって長生きしたいと願っていると思います。2000(H12)年の日本人の平均寿命は男(77歳)女(8
4歳)でともに世界一であり、長寿を誇っています。ところが、長寿に似つかわしくない歯と口の領域の問題があります。歯の寿命が短いのです。歯の寿命は50〜60数年で、平均寿命と15年前後の差がありますので、高齢者にとって食べる楽しみに制約が付きまといます。
我が国では、1989(H
元)年の「8020(ハチマルニイマル)運動」が提唱されました。その後、全国的な規模で歯を残す運動が繰り広げられていますが、1999年の全国規模の調査で「8008」であります。
また、2000年3月に、「
21世紀における国民健康づくり運動(健康日本
21)」が策定され、各自治体は国民の健康づくり運動を推進しています。歯と口腔の分野として、「歯の健康」が取り上げられ、ライフステージに応じた適切なう蝕と歯周病の予防を推進することを基本に据えて、生涯を通じた歯と口腔の健康づくりが強調されています。「歯の健康」の第一目標は歯の喪失の防止ですので、「歯の長命」に取り組んで行こうということになります。
「健康日本21」の目標として、(1)歯の喪失の防止(2)幼児期のう蝕予防(3)学齢期のう蝕予防(4)成人の歯周病予防があげられています。その対策の3
本柱は(1)自己管理能力の向上(2)専門家等による支援と定期管理(3)保健所等による情報管理と普及啓発の推進、となっています。そこで、う蝕を予防し、歯を長持ちするという目標を達成するには、適切なフッ化物の利用が行われる必要があります。これは
EBM/EBD科学的な根拠に基づいた最良の方法だからです。「健康日本21
」にも、フッ化物歯面塗布法とフッ化物配合歯磨剤の活用について明記されています。
しかしながら、フッ化物応用の原点である水道水フッ化物濃度適正化(以下、フロリデーション)とフッ化物洗口には言及していません。フロリデーションは自然から人が学んだ方法であり、世界の約
3.6億人は有益な微量栄養素であるフッ化物の供給を受けています。フロリデーションは人々に公平であり、経済性と最も高い安全性を有し、生涯にわたって効果的な方法です。すなわち、公衆衛生的なフッ化物の利用方法が最も自然なのです。
やっと遅まきながら、わが国におけるフロリデーションは産声をあげようとしています。一方、集団フッ化物洗口は約
2%のこどもたちに提供されているに過ぎません。フッ化物配合歯磨剤の市場占有率も 70%台後半で頭打ちの状態です。フッ化物歯面塗布も限定的と言えましょう。
すべての人々の快適な暮らしを支援して素敵な笑顔で満たされるように、
20世紀の歯科医学の研究と臨床および地域実践の成果を総括し、すべての人々がフッ化物を活かすことのできるような環境づくりこそが、現在及びこれからの日本に求められています。まずもってその実践こそ、口腔領域からの健康長寿への多大な貢献につながるものと考えます。
|
田浦 勝彦先生の ご略歴
昭和22年生まれ。昭和41年3月に、長崎県立長崎東高等学校卒業、昭和49年3月福岡県立九州歯科大学を卒業され、6月文部教官(東北大学助手)。昭和56年歯学博士学位取得『保育園児における乳歯齲蝕と刷掃習慣について』、昭和57年より文部教官(東北大学講師)で、現在に至る。 |